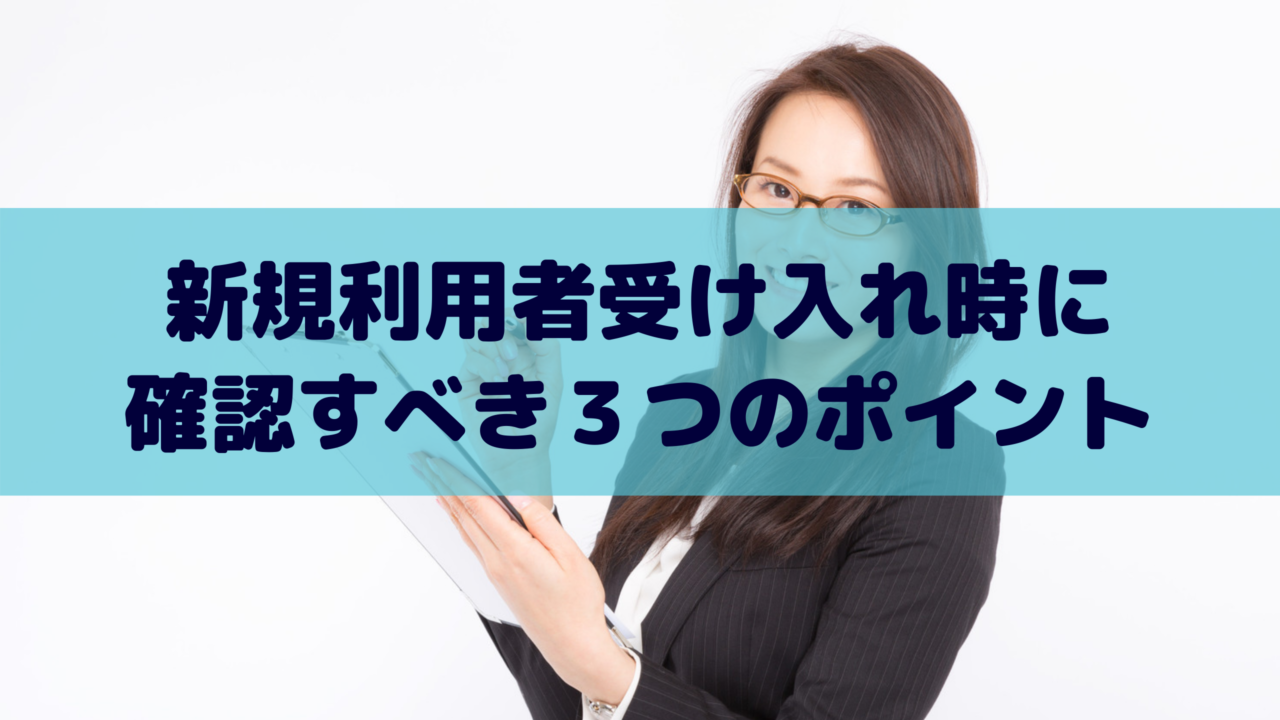このページをご覧になっているあなたは、ショートステイの生活相談員として実際に利用者を受け入れている立場の方だと思います。もしくは、これからショートステイの生活相談員をやっていく方でしょうか。
いずれにしても、少なからずショートステイの利用者受け入れに対して何かしらの悩みを持っている方だと思います。
もしかしたら、実際に受け入れ時のケアマネとのやりとりがうまくいかなくて、このページにたどり着いたかもしれません。
こんにちは。生活相談員のtakuma(@takuma3104 )です。
わたしは、デイサービスとショートステイの生活相談員をかれこれ10年以上続けています。
生活相談員の仕事に、「新規利用者の受け入れ」というものがあります。ケアマネからの連絡を受け、利用を希望をしている人の受け入れ調整を行います。
ケアマネからはいつ、どんな問い合わせがくるかわかりません。「こっちが忙しくしているときに、ケアマネから新規利用の問い合わせがくる」なんてこともよくあります。
「重要なことを聞き忘れて受け入れの返事をしてしまい、あとで後悔する」ってこともわたし自身、過去にけっこうあります。なかには、重大なことを聞き忘れてしまって後々トラブルになってしまったこともあります…。
そうならないように、ここでは後々トラブルにならないように、利用者の受け入れ前に確認しておくべきポイントを、3つご紹介したいと思います。
医療行為
まず確認するのは、「医療行為」の有無です。
特に引っかかってくるのは、「胃ろう」「インスリン」「褥瘡の処置」「吸引」「酸素」です。
たとえば、胃ろうの場合です。
「胃ろうの人なんですけど、ショートステイで受入れてもらえませんか?」
ケアマネからの問い合わせ胃ろうを理由に受入れ拒否はできない
ただ、胃ろうの人ひとりを受入れることで、看護職員の負担が爆発的に増えてしまいます
結果的に施設が回らなくなってしまうため、受入れは制限せざるを得ません— takuma@生活相談員 (@takuma3104) September 8, 2020
胃ろうの利用者を受け入れることによって、職員、特に看護職員の負担が増えてしまいます。
「それを受け入れるのがショートステイの仕事だろ」
という考えもあるかもしれませんが、現実として理想論だけではやっていけないことがあるんです。
医療行為のある利用者を何人も受け入れてしまうと、そのぶん看護職員の負担が重くなり、ほかの利用者へケアが行き届かなくなります。
配薬や服薬ミス、体調確認などの業務が手薄になってしまうこともあります。
結果として現場が回らなくなってしまうのです。
「医療行為を理由に利用者の受け入れを制限することはできない」と言われますが、ではショートステイの入所者全員に「インスリン」「胃ろう」「褥瘡処置」などの医療行為が必要だったら、「そんなショートステイ回していけますか?」って話になります。
完全にパンクしてしまいますよね。
ですから、医療行為のある利用者をやみくもに受け入れることはできません。
施設運営のために、「医療行為」の必要な利用者は意図的に制限をしなければならないのが現実なのです。
生活相談員としては、医療行為の有無を確認をせず安易に受け入れてしまうと
“実は医療行為が必要で、現場が回らない。看護職員からは大ブーイング。”
ってことがあります。
わたし自身、過去に何度もあります。
結果的にその人を受けるにせよ受けないにせよ、医療行為の有無で現場の負担は大きく変わってきますので、受け入れ調整をする際にはきちんと確認をするとよいでしょう。
また、医療行為がなくても「末期がん」や「食事があまりとれていない」といったアブナイ人を、ケアマネが紹介してくるケースがあります。
ケアマネはショートステイをすすめてきますが、「ちゃんとケアマネジメントしてるの?」「そんな状態でショートステイ大丈夫なの?」っていう疑問がわきます。
この場合は「その人にショートステイというサービスが適切なのか」ということから考える必要がありますので、ケアマネにやんわりと、「その状態って、ショートステイじゃないんじゃないですか」って話を振ってあげてください。
迷惑行為
受け入れ前に確認しておくべきことの2つ目は、「迷惑行為」の有無です。
性格や精神疾患、認知症などにより、ほかの利用者に迷惑を及ぼす可能性があると判断される場合は、利用をお断りすることもあります。
ケアマネからデイサービス利用の相談
聞けば、他利用者への迷惑行為で市内数ヶ所の事業所を出入り禁止となってる人とのことここでうちが受ければその人とケアマネは嬉しいのでしょうが
その代償は大きい
今いる利用者を犠牲にしてまで受けるべきなのか?判断分かれると思いますが
うちは無理だなー— takuma@生活相談員 (@takuma3104) January 16, 2020
迷惑行為をする人を受け入れることにより、その人と家族、ケアマネには喜ばれるかもしれません。
しかし、その人が入所したことによってショートステイを利用しているほかの人が迷惑を被ることになるとしたら…。
受け入れをためらってしまいますよね。
個人の利益を守るのは大切ですが、それ以上に全体の利益を守る役割がショートステイにはあるわけです。
「その他大勢の利用者の利益を守るためには、迷惑行為のある利用者を受け入れないという判断も致し方ない」というのが私の見解です。
「“問題行動”のある利用者の受け入れについて」はこちらのページでも解説しています。↓↓↓
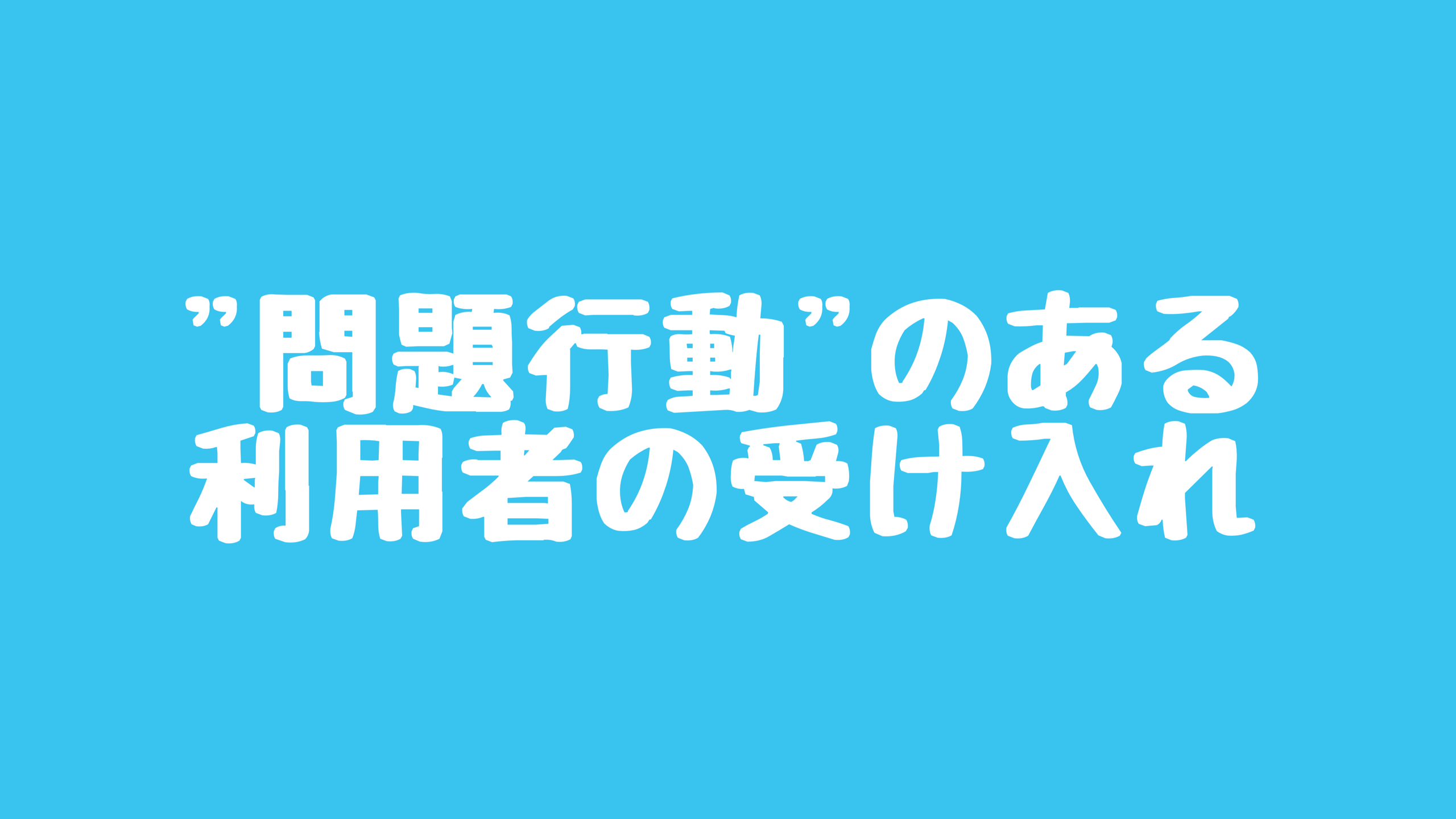
実は「迷惑行為」のようなマイナスの情報って、こちらから聞かないとあまり詳しく教えてくれないケアマネがいます。
察するに、迷惑行為があると受け入れてもらえないから、あえて言わないようにしているんだと思います。
「あえて言わない」ということですから、ウソをついているわけではありません。
ケアマネを責めることはできないでしょう。
ですが、受ける側にとって迷惑行為の情報は超重要項目です。
ケアマネが言いたくないのなら、相談員のほうから積極的に情報を聞き出していく必要があります。
なので、ケアマネの話の中で少しでも引っかかるところがあったら、深堀りして聞いていくようにしましょう。
転倒リスク
受け入れ前に確認しておくべきこと、3つ目は「転倒リスク」です
転倒リスクがあるからといって、それを理由に利用をお断りすることはできません。
しかし、生活相談員としてはあらかじめそのリスクについて家族に伝えておく必要があります。そして、
「転倒を100%防ぐことは不可能である」
これを家族にわかってもらったうえで、利用してもらうようにします。
そして、もし理解を得られないようであれば、最悪は利用を遠慮していただくこともあります。
確実にトラブるので。
また、どんなに家族が理解を示してくれたとしても、あまりにも転倒リスクが高すぎるようであれば、利用を見合わせるケースもあります。
どんなに安全策を講じて、
どれだけ家族の理解が得られていたとしても、利用中に転倒・骨折があれば、それはもう「事故」なのです。
保険者に事故報告書を出さなければなりませんし、施設として「再発防止」を検討しなければならないのです。
「どう頑張ってもうちのショートステイのキャパシティでは防げない」っていう人もいるのです。
なかには「職員ひとりひとりが優秀で設備も充実、どんなに転倒リスクのある利用者でも受け入れ可能です」というショートステイがあるかもしれません。
ですが、うちを含め多くのショートステイは、お世辞にも全員が全員優秀であるとはいえません。
限られた人材で何とか回しているのが現状でしょう。
それは構造上仕方ないです。
だって、介護業界は給与が安くて優秀な人材があまりいないんですから。
転倒・骨折という事故があったときに責任をとるのは、国でも自治体でもありません。その利用者を預かっていた施設です。
そして、苦情対応の窓口は他でもありません。生活相談員であるあなたです。
誰も守ってくれません。
ですから、あらかじめできる範囲でリスク管理はしておきましょう。
それでも、転ぶときは転ぶんです。
↓そんなときはコチラ↓
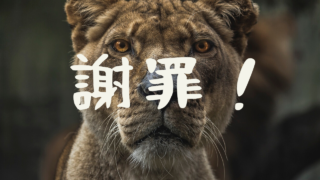
~まとめ~施設のキャパを超えない範囲で受け入れる
さいごに、ここでの内容のまとめをしたいと思います。
生活相談員が利用者を受け入れる際に気をつけたいことは、「自分たちのキャパシティを超えない範囲で受け入れる」ということです。
もちろん、なんでもかんでも断っていては誰も利用してもらえなくなりますし、職員も成長できません。ときには、リスクを冒しても受け入れることが必要な場合もあります。
ですが、基本的には施設のキャパシティを超えてまで受け入れないほうがよいです。
そのためには、まず自分の施設のキャパシティを把握しておくことが必要です。
そして、先に挙げた「医療行為」「迷惑行為」「転倒リスク」の項目を中心に確認をし、難しいと思われるケースについては「断る」ということも選択肢に加えておくことです。
無理して受け入れても、いいことはありません。
無理して受け入れた結果トラブルが起きて迷惑がかかるのは、その受け入れた利用者であり、そのケアマネ、そのほかの利用者や職員、そしてなによりその利用者の受け入れを調整したあなた自身です。
ショートステイにかかわる人が幸せに過ごせるように、利用者を受け入れるにあたっては、たとえ忙しい中でもポイントを押さえて丁寧に行いたいものです。