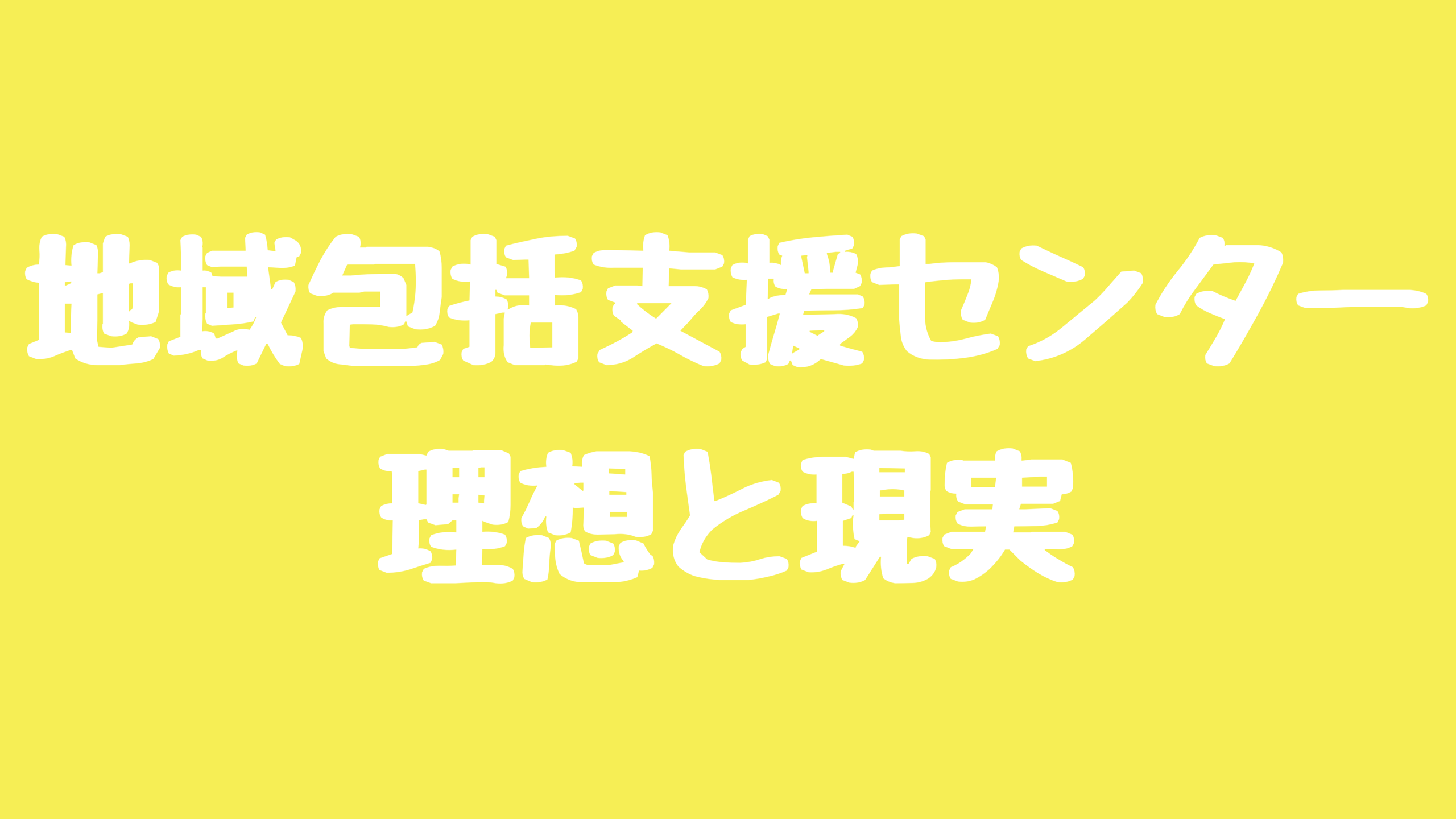こんにちは。生活相談員のtakuma(@takuma3104 )です。
わたしの勤務する自治体では、2020年4月1日から地域包括支援センターに愛称がついたんです。
うちの市の地域包括支援センターが、来月から「高齢者支援センター」って愛称をつけるそう
理由は「地域包括支援センターでは、高齢者を支援していることがわかりにくいため」とのこと…
気になって調べてみたら、最近は地域包括支援センターに愛称をつけてる自治体がけっこうあるんですね
— takuma@生活相談員 (@takuma3104) 2020年3月12日
「包括に愛称をつけられる」なんて話聞いたことがなかったので、気になって調べてみました。
「地域包括支援センター 愛称」で検索してみたら、けっこう多くの自治体が地域包括支援センターに愛称をつけているようです。
愛称をつけること自体をわたしは否定しないのですが、
地域包括支援センターの愛称を、
「高齢者支援センター」や「おとしより相談センター」みたいに
「高齢者」押しでいくスタンスって、ちょっとどうなのかな?
との思いで、この記事を書いております。
はい、そうです。
だいぶニッチな内容となっております。
狭い話なのですが、もし気になった方がいれば、読み進めていただけるとうれしいです。
愛称をつけたらわかりやすくなるのか?
わたしの勤務する自治体が「高齢者支援センター」なる愛称をつけた意図は、
「主に高齢者を支援していることがわかりにくいことから、市民への理解促進を図るため」
に制定したそうです。
ここでわたしが思ったのは、
もし「地域包括支援センター」という名称が「わかりにくい」という大きな流れがあるのであれば、
自治体レベルでなく根本から変えたらよいのではないのでしょうか?
自治体間で名称に差のある状況って、果たしてわかりやすさにつながるのか?
むしろわかりにくくなるのではないか?
って疑問すら湧きます。
ちなみに、私の勤務する自治体に問い合わせたところ、担当者からは
「市民からわかりにくいとの声はなく、実は他の自治体もやっているから右へならえで愛称をつけました」
って回答があって、衝撃的でした…
そもそも地域包括支援センターの役割とは?
「高齢者支援センター」という愛称は、地域包括支援センターが主に高齢者の支援機関であることをわかりやすく表現した、という説明でありました。
確かに“主に”は高齢者の支援機関かもしれません。
設置の根拠法も介護保険法ではあります。
ですが、以下の文章をご覧ください。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の地域住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の包括的保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されるものである(介護保険法第115条)。
ここにあるように、地域包括支援センターの対象は、高齢者ではなく地域住民です。
つまり、地域包括支援センターに求められる役割は、地域包括ケアの推進なわけです。
高齢者支援という枠を超えて、広く地域の福祉を推進するための機関であることは言うまでもありません。
ですので、あえて高齢者支援という言葉を使い、地域包括支援センターの守備範囲を狭めるような相性のつけ方をするのは、適切でないような気がします。
「高齢者支援」だけっていう印象を与えてしまうのは、むしろマイナスかと…
たかが名前ですが、言葉には言霊が宿ります。
普段使う言葉はその言葉を使う人の思考になり、それが行動として表れていくものです。
地域包括支援センターを「高齢者支援」に限定してしまうこの愛称は、地域包括ケアの形骸化を加速させているだけのようにしか思えてなりません。。。