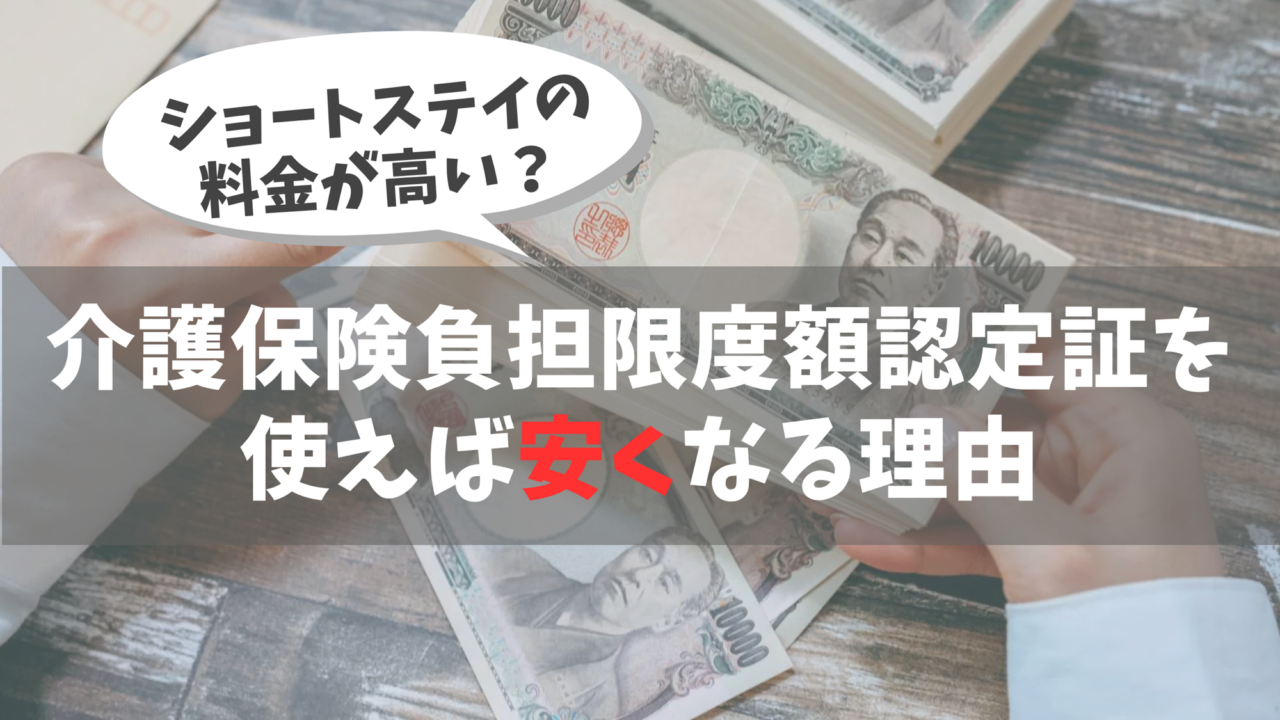「ショートステイを利用したいけど、思ったより料金が高い…」
「介護保険が使えるのに、どうしてこんなにお金がかかるの?」
「少しでも安く利用する方法はない?」
ショートステイの生活相談員として働いている中で、ご利用者やご家族からこのような相談を受けることがあります。ショートステイの料金の中には、介護保険料の他に食費や居住費なども含まれているため、どうしても費用が高くなりがちです。
実は、「介護保険負担限度額認定証」があれば、ショートステイの費用を大幅に抑えることができます。この認定証を取得すると、食費や居住費の負担が軽減され、自己負担額をグッと下げることが可能です。
この記事では、ショートステイの料金の仕組みを解説しながら、「負担限度額認定証を使うとどれくらい安くなるのか」「どうすれば申請できるのか」を紹介します。ショートステイの費用負担を抑えたいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
takuma
生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)
・Xにほぼ毎日投稿しています。
・職業情報サイトへ生活相談員に関する記事提供実績あります。その他介護情報サイトへ記事提供実績もあり。
・kindle出版で『 対人援助一年目の教科書: 現役のプロが書いた実践で役立つスキルと心構え』発売しています。
詳しい自己紹介はこちら。
「対人援助一年目の教科書」 Kindleにて好評発売中です!

対人援助一年目の教科書: 現役のプロが書いた実践で役立つスキルと心構え
ショートステイの料金の仕組み
ショートステイの費用は、大きく分けて以下の3つの項目があり、それぞれに費用が発生します。
① 介護サービス費(介護保険自己負担分)
ショートステイを利用すると、食事や入浴、排泄介助などの介護サービスを受けられます。これにかかる費用は介護保険の適用対象となり、自己負担額は1〜3割です(所得に応じて異なります)。
② 食費(介護保険適用外)
ショートステイでは1日3食の食事が提供されますが、この食事は介護保険が適用されず、全額自己負担となります。施設によって異なりますが、1日あたり1,500円〜2,500円程度かかるのが一般的です。
③ 居住費(介護保険適用外)
ショートステイの利用中は施設内で宿泊するため、「滞在費」や「部屋代」として居住費がかかります。こちらも介護保険の適用外で、1日あたり1,000円〜3,000円ほどかかる場合が多いです。
ショートステイの費用が高くなる要因
①の介護サービス費には介護保険が適用されるため、自己負担は比較的抑えられます。しかしながら、②食費と③居住費は全額自己負担のため、ここが高額になりがちです。
たとえば、1日あたりの費用をざっくり計算すると…
①介護サービス費(1割負担):約1,000円
②食費:1,800円
③居住費:2,000円
→合計:1日あたり約4,800円
1泊2日利用すると、約9,600円の費用がかかります。
1週間利用すると、約33,600円の負担になります。これが1ヶ月となると、さらに高額になるため、家族にとっては大きな出費です。
「費用負担を減らしたい」「もう少し安くならないの?」と思ったときに活用したいのが、負担限度額認定証です。次の章でこの認定証について解説します。
負担限度額認定証とは?
介護サービスには介護保険が適用されますが、食費や居住費は介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。そこで頼りになるのが「介護保険負担限度額認定証」です。
介護保険負担限度額認定証があると、介護保険サービスを利用する際に、食費や居住費などの自己負担に上限を設けることができます。これは、一定の所得以下の人が、ショートステイや特養などの介護施設を利用しやすくなるための仕組みです。
通常、ショートステイでは食費や居住費が全額自己負担となりますが、介護保険負担限度額認定証を取得すると、上限額(負担限度額)が設定され、所得に応じて自己負担額を軽減することができます。
負担限度額認定証を使えばどれくらい安くなる?
では、介護保険負担限度額認定証によって、どれくらいショートステイの自己負担額を軽減することができるのでしょう?
介護保険負担限度額認定証を取得すると、所得に応じて第1段階・第2段階・第3段階①・第3段階②・第4段階(対象外)の5段階に分かれ、負担限度額(上限額)が適用されます。
以下は、ショートステイで適用される食費・居住費の負担限度額です。(参考:厚生労働省 介護保健施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります)
| 区分 | 食費(1日) | 居住費(多床室) | 居住費(従来型個室) | 居住費(ユニット型個室的多床室) | ユニット型個室 |
| 第1段階 | 300円 | 0 | 380 | 550 | 880 |
| 第2段階 | 600円 | 430 | 480 | 550 | 880 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430 | 880 | 1,370 | 1,370 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430 | 880 | 1,370 | 1,370 |
| 第4段階(対象外) | ー | ー | ー | ー | ー |
たとえば、第3段階②の認定を受けたときの料金は…
①介護サービス費(1割負担):約1,000円
②食費:1,300円
③居住費:430円(多床室)
→合計:1日あたり約2,730円
負担限度額認定証がない場合の1日あたりの利用料金は約4,800円でしたから、1日あたり2,070円安くショートステイを利用することができます。
取得する条件と申請方法
介護保険負担限度額認定証を取得するためには、所得や資産が一定基準以下である必要があります。以下の条件を全て満たす場合に取得が可能です。
① 住民税非課税世帯であること
まず、住民税非課税世帯であることが、負担限度額認定証の取得条件です。
② 所得基準を満たしていること
本人の年金収入額や所得額に応じて、下記の通り負担限度額の区分が決まります。
| 区分 | 所得要件 |
| 第1段階 | 生活保護受給者または年金受給者で住民税非課税世帯 |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で、本人の合計所得と年金収入の合計が80万円以下 |
| 第3段階① | 住民税非課税世帯で、本人の合計所得と年金収入の合計が80〜120万円以下 |
| 第3段階② | 住民税非課税世帯で、本人の合計所得と年金収入の合計が120万円超 |
| 第4段階(対象外) | 上記以外 |
③ 預貯金の上限額
預貯金額にも基準があります。以下の金額を超えている場合、認定を受けることができません。
| 区分 | 預貯金額要件(夫婦の場合) |
| 第1段階 | なし、または1,000万円以下(2,000万円以下) |
| 第2段階 | 650万円以下(1,650万円以下) |
| 第3段階① | 550万円以下(1,550万円以下) |
| 第3段階② | 500万円以下(1,500万円以下) |
| 第4段階(対象外) | ー |
申請方法
介護保険負担限度額認定証を取得するためには、市区町村の役所(介護保険担当課)に申請書を提出する必要があります。以下の手順で手続きを進めます。
①必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です。
・介護保険負担限度額認定申請書(役所で入手可能)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・収入を証明する書類(所得証明書など)
・預貯金残高を証明する書類(通帳のコピー、残高証明書など)
②申請書類の提出
必要書類がそろったら、住んでいる市区町村の役所(介護保険担当課)に提出します。窓口での提出以外にも、郵送やオンライン申請が可能な自治体もあります。
③審査・認定
市区町村が所得状況と預貯金額を審査し、条件を満たしていれば負担限度額認定証が交付されます。自治体によって異なりますが、申請してからおおむね1週間程度で郵送されます。
④受け取り
審査が完了すると、郵送で負担限度額認定証が届きます。認定証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。継続して利用する場合には、再度申請が必要になります。
認定証を受け取ったら、ショートステイの事業所に提出します。持っているだけでは安くなりませんので、注意が必要です。
まとめ
介護保険負担限度額認定証を取得することで、ショートステイの費用を軽減することができます。複雑な手続きではないので、該当しそうな方は市区町村に相談することをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
◆ 生活相談員の基礎知識はこちら
◆ おすすめ書籍はこちら![]()
◆ さらに深く学ぶなら
・本気で学ぶケアスタッフのための総合オンラインセミナー.『ケアラル』
◆ 介護の資格・転職なら