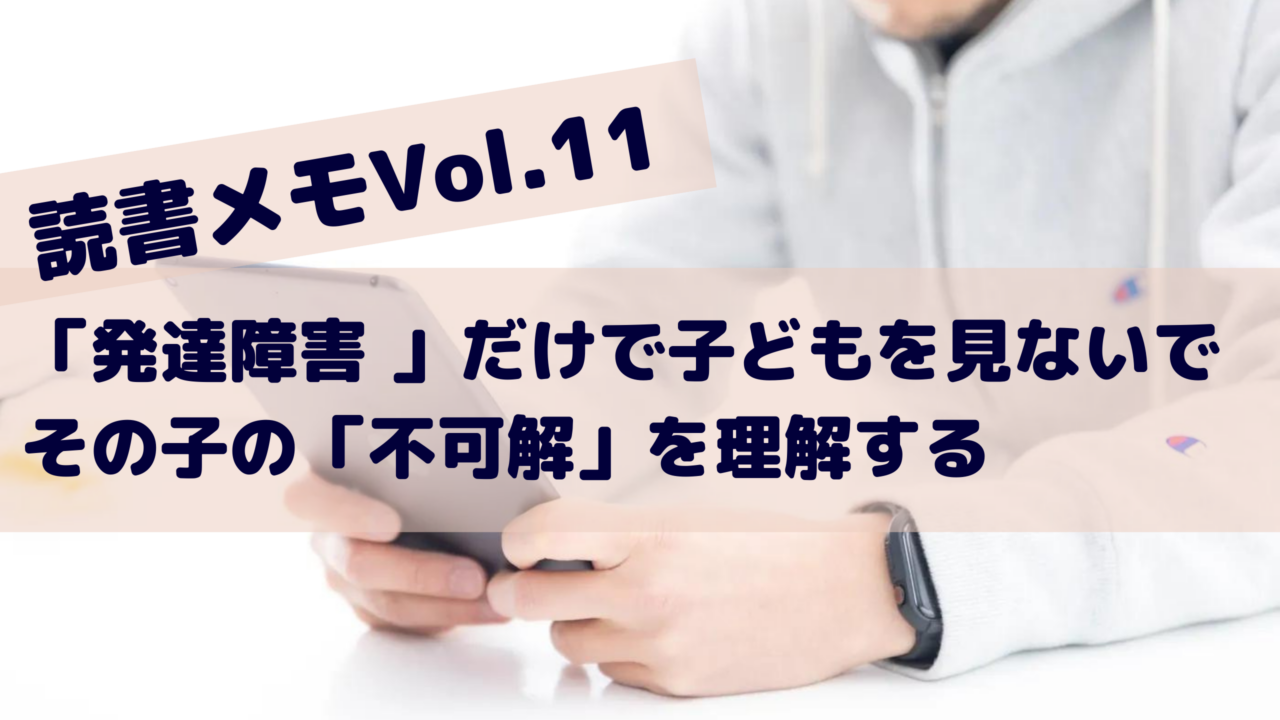※当サイトではアフィリエイト広告を使用しています
本書の概要
読書記録
この本を読んだ理由
長男がADHDであり、ADHDへの理解を深めたいという思いがあった。本書を読んだとき長男は保育園の年長で、翌年には就学を控えていた。就学についてどのように考えたらよいか悩んでいたので、参考になればと思い読んだ。2021/5/25読了。
100文字要約
発達障害と診断することが診療の目的ではない。診断があってもなくても、その子の生活の質を上げるためにできることをやっていこう。12のストーリーで展開され、幼児期~就学時期~学童期それぞれの困りごとへの解決イメージが湧きやすい。
本書から得た知見
① ADHD児の特徴
- 12歳までに、2か所以上で6か月以上にわたり認められ、他の障害の経過中の症状では説明できない、並外れた不注意・多動性・衝動性がある。
- 自分でもわかっているが、自己制御できない。うまくできないことのもどかしさがある。
- ADHD児の親はADHD児に対し常にイライラした関係性を持ちやすく、自責と児への攻撃性が見られる。
② 発達障害児との関わるうえでのポイントは?
ある心配されがちな性分について、不安な面だけでなく、「こういう面もあるよね」「裏を返せばこんないい面でもあるよね」という見方を伝える。たとえば、「無鉄砲」→「チャレンジ精神がすごい」 「一目散に突き進む」→「猪突猛進。その目のつけどころと俊敏さ、なかなかいいよね」といったように。
③ 就学時における選択肢は?
- 通常学級:支援の必要な子には、少人数指導など可能な範囲で支援を受けられる場合もある。
- 通級による指導:通常学級に在籍しながら、週に1回程度、通常学級から離れて個別の指導を受ける。
- 特別支援学級:小学校内に学級があり、心身に障害または発達に偏りがある子が対象。少人数に対し複数の担任が配置されている。
- 特別支援学校:比較的障害の程度が重い子を対象に、専門性の高い教育を行う。
キラーフレーズ
乳幼児期は、親がいかに「子どもの行動を理解し、必要な環境を用意していくか」ということに苦心してきましたが、学童期の途中から少し変わってきます。「この子はこの先どうやって生きていくのだろう」というふうにテーマが変化してきて、思春期に向けて徐々に子どもの「自立力」が問われるようになってくるのです。(p.133)
本を読むなら電子書籍の〈Kindle〉がおすすめです。さらに月額980円の〈Kindle Unlimited〉なら対象の本12万冊が読み放題。
Kindle Unlimited(キンドル アンリミテッド)
「本を読みたいけど時間がない」という方には、〈Amazonオーディブル〉という「耳で読む」本がおすすめです。月額1,500円で12万以上の作品が聴き放題。