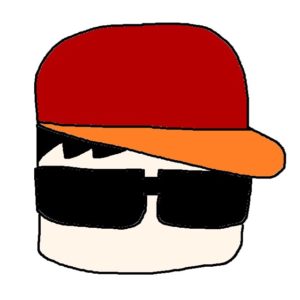わたしには、3つ下のおとうとがいます。
おとうとは、重度の知的障害をもって生まれてきました。
おとうとに対して感じていたわたしの気持ちを、ここで打ち明けたいと思います。
わたしは、おとうとの存在が恥ずかしかったです。
小学校のときの体験
わたしの小学校のときの同級生に、軽度の知的障害のある女の子がいました。
当時、わたしの通っていた小学校には「あいご学級」というものがあったんです。
「あいご」は漢字で書くと「愛護」という字です。
「あいご学級」とは、いわゆる「特別支援学級」みたいなもので、その子は普段はみんなと一緒のクラスにいたのですが、一部の時間だけはその「あいご学級」に行って勉強していました。
その子とは、同じクラスメイトとして一緒に授業を受けてはいるんですが、たまに別授業でその「あいご学級」にいったりしてたんですよね。
で、その子がいじめられてたんです。
クラスメイトから、「あいご」「あいご」と呼ばれ、よくからかわれていました。
ここでわたしが、「障害について理解のある生徒として」その子をかばえたらかっこよかったのかもしれませんが、当時のわたしはそんなに強い子どもではありませんでした(今もです…)
積極的にいじめに加担するわけではないものの、見て見ぬふりをする小学生のわたし。
そして、なによりもわたしが不安でたまらなかったことは、「自分もおとうとのことを話すといじめられるんじゃないか」ということでした。
おとうとの存在が恥ずかしいわたし
同級生の女の子がいじめられているのを見て、わたしは障害のあるおとうとの存在を考えるようになりました。
うちのおとうとは周りとちょっと違うけど、それが差別やいじめの対象になるなんて、それまでは思っていなかったんだと思います。
「自分のおとうとも、その子と同じで知的障害がある」
「むしろその子よりも程度が重い」
「もしもそのことがみんなにバレたら、自分はみんなからバカにされてしまうのではないか」
「自分はいじめられたくない」
当時のわたしの気持ちを言語化するとしたら、こんな感じだと思います。
そしてわたしは、おとうとの存在を周りからひた隠しするようになりました。
わたしのおとうとはわたしと同じ小学校ではなく、当時でいう養護学校に通っていましたので、わたしがおとうとの話をしなければ、周りはおとうとの存在を知ることはありません。
でも、同級生との会話の中で、まったくきょうだいの話をしないわけにもいきません。
話の流れで、きょうだいの話になることがあります。
そうなると、つい口ごもってしまう。
そして、なんとなく場から離れてしまう。
そうするうちに、いつしか積極的なコミュニケーションができなくなっていき、あまり自分の思いを発言することがなくなっていったように思います。
友だちとの会話の中で自分きょうだいの話ができないのは、今思うとけっこうつらかったんじゃないかなぁ。
おとうとへの思いと両親への思い
おとうとの話ができないということは、無意識的にわたしのなかで、おとうとや両親への敵意となっていきました。
「そもそも、なんでおとうとのせいで自分がこんな嫌な思いをしなければいけないんだ」
「自分は何にも悪くないのに、なんでおとうとは知的障害をもって生まれてきてしまったんだ」
わたしは、弟のことが嫌いになっていきました。
これ、当時はそんなこと意識できていませんでした。
おとなになって振り返ったときに、そう思いました。
そして、おとうとに対してのわたしの気持ち、両親には言えませんでした。
両親の大変さも、間近で見ていたわけですから。
両親はどうしてもおとうとに手がかかります。
わたしは、子どもながらに我慢するわけです。
そうして、無意識のうちに「おとうとは一番、おにいちゃんは二番」という二番手意識が育っていきます。
そして、両親に認めてもらいたくて、「いい子」を演じてしまうんですよね。
両親としても、「おとうとの分まで頑張ってほしい」っていう、わたしへの期待が大きかったんじゃないかなぁと思ってます。
「おとうとは知的障害で、いわゆるふつうの生き方はできない。
だからせめておにいちゃんは、立派に成長してほしい。」
親がそう思っていたかどうかはわかりませんし、聞いたこともないですが、少なくともわたしは無意識に両親からこんなメッセージを受け取っていたのだと思います。
いま
そして今、わたしはおとなになって結婚して、ふたりの子どもも生まれました。
今でこそそれなりに楽しく暮らしていますが、10代~20代の頃はおとうとのことや家族のことで葛藤し、悩むことが多々ありました。
ここでは、わたしが子どものころ、おとうとに対して感じていたことを書いてみました。
他にも、進路選択や恋愛、結婚、人づきあいなど、きょうだい児であることで思い悩んだことはそれなりにありましたので、またの機会に書きたいと思っています。
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。